企業や個人事業主が資金調達を行うための方法はいくつかありますが、近年「クラウドファンディング」という方法が注目を集めるようになってきています。
企業や個人事業主にとっては資金調達の方法はいくらあってもよいので、クラウドファンディングについても、特徴やメリット・デメリットなどを把握しておきましょう。
この記事では、
- クラウドファンディングの種類5つ
- クラウドファンディングで資金調達を行うことのメリット・デメリット
について説明します。
● クラウドファンディングのメリットと危険性を理解することができる
● 間違った資金調達による資金繰り悪化を防ぐことができる
● クラウドファンディング以外の資金調達方法も知れて、資金調達の幅が広がる
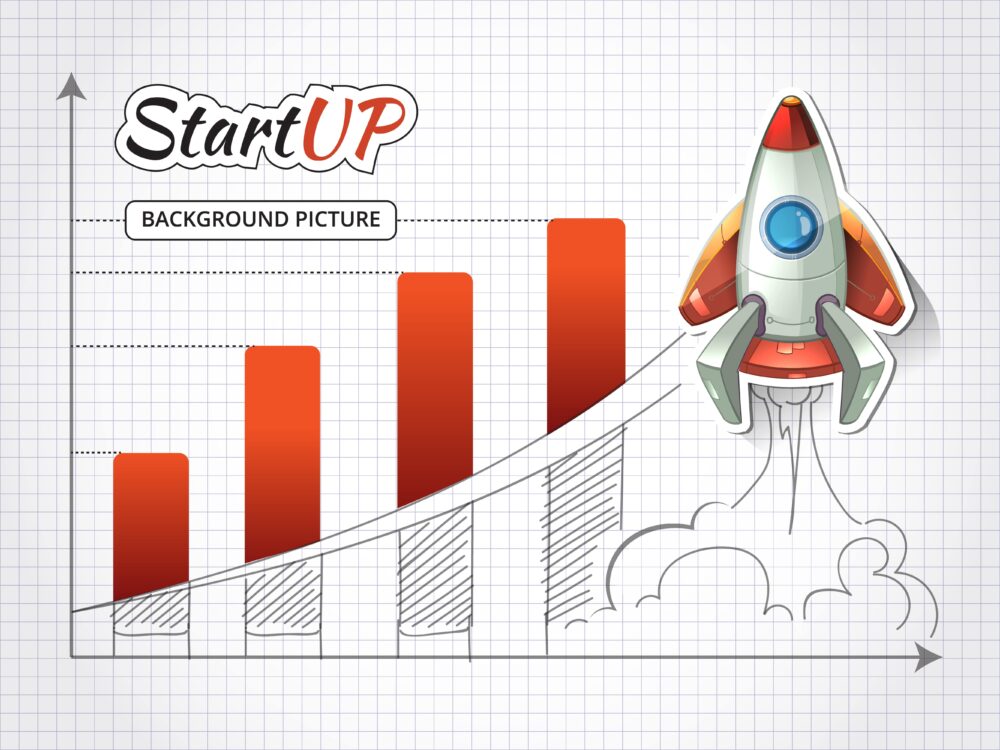
日本政策金融公庫、商工中金、地銀、信用金庫・信用組合の融資は、知識・経験なく「何となく」で進めると必ず失敗します。融資には「金融機関の理解」と「ノウハウと実務経験」が必要です。
融資代行プロは、金融機関出身のコンサルタントが「成果報酬型1%~」で融資コンサル/代行するサービスです。これまで5,500社以上の融資相談を受け「200万円〜9.5億円の融資成功」の実績を挙げてきました。
そんな私達に無料の融資相談をしませんか?詳細は下記ページをご覧ください。
成果報酬型の融資コンサルはコチラ>
\「銀行融資に強い」相談先はコチラ/
※【毎日 限定5名まで!!】
クラウドファンディングは「不特定多数の人から資金を募る資金調達手法」
クラウドファンディングとは、インターネット上で新しい商品やサービスなどに関する情報をプロジェクトとして公開し、その内容やコンセプトに賛同・共感してくれる不特定多数の人から資金を募る方法です。
「群衆」を意味する「crowd」と、「資金調達」を意味する「funding」を組み合わせた造語であり、近年新しい資金調達の方法として注目を集めています。
専用のサイト上で行われるのが一般的であり、クラウドファンディングを行うことができるサイトは、その数をどんどん増してきています。
5つのクラウドファンディングの種類(購入・寄付・融資・株式投資・ファンディング型)
クラウドファンディングには、手がけるプロジェクトの方向性や出資者に対する見返り(リターン)の種類などに応じて、以下5つの種類があります。
▼クラウドファンディングの種類
- 種類1. 購入型クラウドファンディング
- 種類2. 寄付型クラウドファンディング
- 種類3. 融資型クラウドファンディング
- 種類4. 株式投資型クラウドファンディング
- 種類5. ファンド型クラウドファンディング
それぞれの種類について、詳しく解説してきます。
種類1. 購入型クラウドファンディング
購入型では、プロジェクトに出資者してくれた人へのリターンとして、プロジェクトで手がける商品やサービスなどが設定されます。お得なサービスを割安で利用できたり、まだ一般には販売されていないような商品を一足早く利用できたりする点が、出資者にとってのメリットです。
一般的にクラウドファンディングという場合は、この種類のことを指すケースが多いです。
種類2. 寄付型クラウドファンディング
言葉の通り「寄付」を原資にしたクラウドファンディングであり、被災地の支援や絶滅危惧種の保護活動など、社会貢献性の高い内容のプロジェクトが多いのが特徴です。
クラウドファンディングでは、出資者に対して何らかの商品やサービス、場合によっては現金などのリターンが設定されていますが、寄付型ではリターンが設定されないことが多いです。
その代わりに、プロジェクトの活動報告やお礼のメッセージなどをリターンとして設定することが多くなっています。
種類3. 融資型クラウドファンディング
融資型では、出資者から集められたお金がサイト運営者によってとりまとめられて、プロジェクト起案者に融資が行われます。起案者はそのお金をもとにして事業を進めますが、融資を受けているため一定の間隔で利息を支払う必要あり、その利息が支援者にとってのリターンとなります。
「ソーシャルレンディング」という名前で知られていることも多く、中小企業や個人事業主にとっては貴重な資金調達の方法の1つです。
種類4. 株式投資型クラウドファンディング
株式投資型では、リターンとしてプロジェクトを起案した企業の未公開株が設定されます。株式上場していない会社でもまとまった資金を調達できる可能性のある方法であり、出資者にとっては出資の幅を広げるための貴重な手段です。
購入型などと比べると、企業の成長次第でリターンの価値が大きく変動するので、出資者として利用する場合は、その点もよく考えておかなければなりません。
種類5. ファンド型クラウドファンディング
ファンド型は、プロジェクトの収益による「分配金」がリターンの原資となっている点が、ほかの系統のクラウドファンディングとは大きく異なります。プロジェクトがうまくいけばリターンは増えますが、逆にプロジェクトの進捗がイマイチだとリターンは期待できません。
そのためほかのクラウドファンディングと比べると、プロジェクトの状況や進捗に関して、出資者のチェックが厳しくなる傾向にあります。
「クラウドファンディングで資金調達」が注目される理由は、気軽に大きな金額を集められる+マーケティング要素も含まれているから
日本で初めてクラウドファンディングサイトがオープンしたのは、2011年です。当初はまだ資金調達の方法としての存在感はそこまでありませんでしたが、少しずつ世に知られるようになっていき、クラウドファンディングがおこなえるサイト(プラットフォーム)の数も徐々に増えていきました。
そして近年、調達金額が億を超えるような大型の調達を成功させるプロジェクトも増えてきており、資金を調達したいと考えている企業や個人事業主からの注目度がアップしてきています。
また、クラウドファンディングの活動を通して、「プロジェクト(サービス)が流行る可能性はあるのか?」といった、単なる資金調達方法ではわからなかったマーケティング情報が入ってくるのも魅力であり、その点がクラウドファンディングが注目されている理由の1つになっているとも考えられます。
クラウドファンディングで資金調達する「3つのメリット」
クラウドファンディングで資金調達をするメリットは、主に以下3つに集約されます。
▼クラウドファンディングのメリット
- メリット1. 融資や出資を受けられなくても資金調達ができる
- メリット2. プロジェクト自体のPRにもなる
- メリット3. テストマーケティングも兼ねることができる
それぞれのメリットについて、説明します。
メリット1. 融資や出資を受けられなくても資金調達ができる
資金調達の方法と言えば、融資や出資などが一般的です。ただ、創業して間もない企業や経営状態が芳しくないような企業の場合は、金融機関から融資を受けるのが難しいです。出資に関しても、ベンチャーキャピタルやエンジェル投資家などが興味を持つような事業を行っていなければ、受けることは難しいでしょう。
融資・出資も期待ができない企業にとっては、プロジェクトに共感してもらえれば資金調達ができるクラウドファンディングは、非常に重宝する方法なのです。
メリット2. プロジェクト自体のPRにもなる
クラウドファンディングで資金調達する場合、どんなプロジェクトに対してお金を出して欲しいのかを、サイト上の専用ページでしっかり説明する必要があります。つまり、必然的に出資者の方がプロジェクトの内容を確認することがになるので、プロジェクト自体のPRにもつながるのです。
結果的に出資にはつながらなくても、プロジェクトページを見た方が友人や知人などに「この前こんなプロジェクトを見て~」と話をしてくれ、そこから出資につながるかもしれません。
メリット3. テストマーケティングも兼ねることができる
購入型のクラウドファンディングでは、出資してもらった金額に応じて商品やサービスなどのリターンを設定します。
類似商品があまりないような商品を手がける場合、その値段設定に苦労することもありますが、出資が集まっているのであれば、商品に対する値段設定はおおよそ合っていると判断できるでしょう。
もちろん通常の購入とクラウドファンディングの出資では前提が異なるので、一般販売する際にはその点も考慮に入れる必要があります。しかし、値段や商品コンセプトに関して事前に消費者の反応を知ることができるのは大きなメリットです。
クラウドファンディングで資金調達する「3つのデメリット」
クラウドファンディングで資金調達をするデメリットは、主に以下3つが挙げられます。
▼クラウドファンディングのデメリット
- デメリット1. アイデアを盗用されるリスク
- デメリット2. 一度募ると取り下げができない
- デメリット3. 出資者が増えると事務手続きが煩雑になる
それぞれのデメリットについて、説明します。
デメリット1. アイデアを盗用されるリスク
クラウドファンディングを行うためには、プロジェクトページを開設してそこにプロジェクトの内容を掲載しなければなりません。
そのため、資金力や開発力のある同業他社にプロジェクトの内容を把握されて、自分たちより先に商品を販売されたりサービスをスタートされたりしてしまう可能性があります。
公開するアイデアに関して特許を取得しておく、社内体制と結びついて初めて実行可能なアイデアにするなど、アイデアを盗用されないように自衛しておくことを心がけましょう。
デメリット2. 一度募ると取り下げができない
クラウドファンディングでは、一度スタートさせたプロジェクトを途中で取り下げることはできません。多くの出資者からの出資を集めたプロジェクトが頓挫してしまうようでは、企業としての信用を失墜させることにもなるでしょう。
プロジェクトが本当に実行可能かどうかを厳密に吟味したうえで、プロジェクトの公開に踏み切りましょう。
デメリット3. 出資者が増えると事務手続きが煩雑になる
クラウドファンディングでは、出資者からの資金をもとにしてプロジェクトをスタートした後、定期的にプロジェクトの進捗などを報告する必要があります。また、リターンとして設定している商品の発送手続きなども行わなければなりません。
こういったことは融資や出資で資金を調達した場合は必要ないことであり、付随する作業が増えることを考慮したうえで、クラウドファンディングを行う必要があります。
出資者の数が多くなればなるほど事務手続き作業も煩雑になるので、場合によっては事務員を臨時で雇わなければならなくなる可能性もあるでしょう。
日本政策金融公庫、商工中金、地銀、信用金庫・信用組合の融資は、知識・経験なく「何となく」で進めると必ず失敗します。融資には「金融機関の理解」と「ノウハウと実務経験」が必要です。
融資代行プロは、金融機関出身のコンサルタントが「成果報酬型1%~」で融資コンサル/代行するサービスです。これまで5,500社以上の融資相談を受け「200万円〜9.5億円の融資成功」の実績を挙げてきました。
そんな私達に無料の融資相談をしませんか?詳細は下記ページをご覧ください。
成果報酬型の融資コンサルはコチラ>
\「銀行融資に強い」相談先はコチラ/
※【毎日 限定5名まで!!】
クラウドファンディングを成功させる「3つのコツ」
手間や時間をかけてクラウドファンディングを行うからには、必ず資金調達を成功させたいところです。
クラウドファンディングでの資金調達を成功させるコツとしては、以下のようなことが挙げられます。
▼クラウドファンディングを成功させるコツ
- コツ1. 知名度・集客力の高い大手サイトを利用する
- コツ2. 魅力的なリターンを設定する
- コツ3. SNSなどで積極的に情報発信する
それぞれについて、説明します。
コツ1. 知名度・集客力の高い大手サイトを利用する
クラウドファインディングで出資をする側からすると、名前も聞いたことがないサイトを使うよりも、知名度がある大手サイトを優先的に選ぶのは自然がことです。つまり、クラウドファンディングでは、知名度がある大手サイトの方が結果的に出資者に見てもらいやすい集客力の高いサイトであると言えます。
どれだけ素晴らしい内容のプロジェクトであっても、出資者の目に留まることがなければ、出資してもらう機会は訪れません。特別なこだわりがないのであれば、なるべく知名度があって大手のサイトを選ぶとよいでしょう。
コツ2. 魅力的なリターンを設定する
出資者はプロジェクトの内容自体もさることながら、どのようなリターンが設定されているかについても、入念にチェックします。自身のお金を出資するのであれば、なるべく魅力的なリターンを受け取りたいと考えるのは当然のことです。
そのため、ほかのプロジェクトでどのようなリターンが設定されているかなども参考にしながら、出資者に食いついてもらえそうなリターンを設定することを心がけましょう。
ただ、出資金額に対して高価すぎるリターンを設定してしまうと、プロジェクト自体の収支計画が狂ってしまう可能性があるので、バランスは重要です。
コツ3. SNSなどで積極的に情報発信する
クラウドファンディングでは、決められた期間内に設定金額以上の出資を集める必要があります。
上述したように、出資を集めるためには出資者の目に留まることが重要です。プロジェクトが公開されている期間中は、SNSなどで積極的に情報発信を行いましょう。SNSの投稿をきっかけに、クラウドファンディングでのプロジェクトについて知っている人が増えてきたら、目標金額も達成しやすくなります。
日本政策金融公庫、商工中金、地銀、信用金庫・信用組合の融資は、知識・経験なく「何となく」で進めると必ず失敗します。融資には「金融機関の理解」と「ノウハウと実務経験」が必要です。
融資代行プロは、金融機関出身のコンサルタントが「成果報酬型1%~」で融資コンサル/代行するサービスです。これまで5,500社以上の融資相談を受け「200万円〜9.5億円の融資成功」の実績を挙げてきました。
そんな私達に無料の融資相談をしませんか?詳細は下記ページをご覧ください。
成果報酬型の融資コンサルはコチラ>
\「銀行融資に強い」相談先はコチラ/
※【毎日 限定5名まで!!】
クラウドファンディングでよくある質問(Q&A)
クラウドファンディングについて、筆者がよくもらう質問について共有いたします。
クラウドファンディングのメリット・デメリットを把握し、スムーズに資金調達をしよう
クラウドファンディングでの資金調達は、審査を受ける必要もなければ、企業としての歴史や信用力を必要ともしません。そのため、中小企業や個人事業主の方にとって非常に魅力的な資金調達の方法です。
メリットとデメリットの双方が存在するので、それぞれをきちんと把握してほかの資金調達の方法と比較したうえで、クラウドファンディングで資金調達を行うべきかどうかを判断しましょう。
もしクラウドファンディングも含め、たくさんある資金調達方法から「自社に適切な資金調達方法を模索したい方」は、資金調達代行サービスの「融資代行プロ」にご相談(無料)ください。
「融資代行プロ」のサービスを活用すると、資金調達のプロ人材が、資金調達 一覧にあるさまざまな方法の中から、あなたの会社に有利(ピッタリ)な資金調達方法を模索し、代行してくれるので、「あなたは資金調達業務から解放」されますよ。
日本政策金融公庫、商工中金、地銀、信用金庫・信用組合の融資は、知識・経験なく「何となく」で進めると必ず失敗します。融資には「金融機関の理解」と「ノウハウと実務経験」が必要です。
融資代行プロは、金融機関出身のコンサルタントが「成果報酬型1%~」で融資コンサル/代行するサービスです。これまで5,500社以上の融資相談を受け「200万円〜9.5億円の融資成功」の実績を挙げてきました。
そんな私達に無料の融資相談をしませんか?詳細は下記ページをご覧ください。
成果報酬型の融資コンサルはコチラ>
\「銀行融資に強い」相談先はコチラ/
※【毎日 限定5名まで!!】
_20250924.png)


