融資(借入)の一本化を検討している経営者は、以下のようなお悩みや疑問をお持ちなのではないでしょうか?
銀行借入の、「金利」や「返済額」の負担が重くなってきた…
複数銀行から借入をしており、「返済管理」や「事務作業」が煩雑になってきた…
融資の一本化の、審査のポイントを押さえておきたい。
「資金繰り改善」と「融資(借入)の一本化」には深い関係があるため、融資を受けている経営者は「融資(借入)の一本化」の知識は、必ず押さえておきたいポイントです。
一本化には融資審査が必要ですが、筆者の経験上、融資(借入)一本化の融資審査のポイントは以下3つをおさえて臨むべきだと考えます。
3つの審査ポイント
- ポイント1. 明確な「資金使途」と「融資額」
- ポイント2. 緻密な「事業計画書」と「資金繰り表」
- ポイント3. 担保・保証人をつける(必要に応じて)
筆者は「融資代行プロ」という、成果報酬1%~の融資コンサル会社を経営しており、これまで多くの中小企業の「融資一本化」をご支援し、成功させてきました。

- 資金調達・財務コンサル会社の経営者
1.融資コンサル|融資代行プロ
2.財務コンサル|御社の財務責任者
3.社外CFOサービス|御社の社外CFO
4.事業計画書の作成代行サービス - 経営コンサル会社の経営者
新規事業コンサル|(株)Pro-D-use - その他、エクイティ支援実績なども多数
これまでの支援実績
創業前後の個人/法人〜中堅企業
調達額「200万円」〜「9.5億円」
多業界の資金調達 / 財務コンサル実績
本記事を読むことで、「一本化の審査のポイント」「融資(借入)一本化のメリット・デメリット」について網羅的に理解でき、難易度の高い融資(借入)の一本化をスムーズに行えるようになります。融資の現場で培ったリアルで濃い内容なので、「ブックマーク」して、あとから何度も読み返すことをオススメします。
日本政策金融公庫、商工中金、地銀、信用金庫・信用組合の融資は、知識・経験なく「何となく」で進めると必ず失敗します。融資には「金融機関の理解」と「ノウハウと実務経験」が必要です。
融資代行プロは、金融機関出身のコンサルタントが「成果報酬型1%~」で融資コンサル/代行するサービスです。これまで5,600社以上の融資相談を受け「200万円〜9.5億円の融資成功」の実績を挙げてきました。
そんな私達に無料の融資相談をしませんか?詳細は下記ページをご覧ください。
成果報酬型の融資コンサルはコチラ>
\「融資の一本化」成功率が上がる/
※【毎日 限定5名まで】
「融資(借入)の一本化」する際の「3つの審査ポイント」
融資(借入)の一本化には、金融機関(銀行・信用金庫など)の融資審査に通る必要があります。金融機関側が見ているポイントを押さえておかないと、審査に簡単に落ちてしまうので、必ず理解をしておきましょう。
以下が、「融資の一本化」の3つの審査ポイントです。
3つの審査ポイント
- ポイント1. 明確な「資金使途」と「融資額」
- ポイント2. 緻密な「事業計画書」と「資金繰り表」
- ポイント3. 担保・保証人をつける(必要に応じて)
それぞれ、詳しく解説していきます。
なお、「銀行の融資審査の通過率を上げるコツ」や「銀行融資の必要書類と注意点」について詳しく知りたい方は、以下の記事が参考になるので必ずチェックしておきましょう。

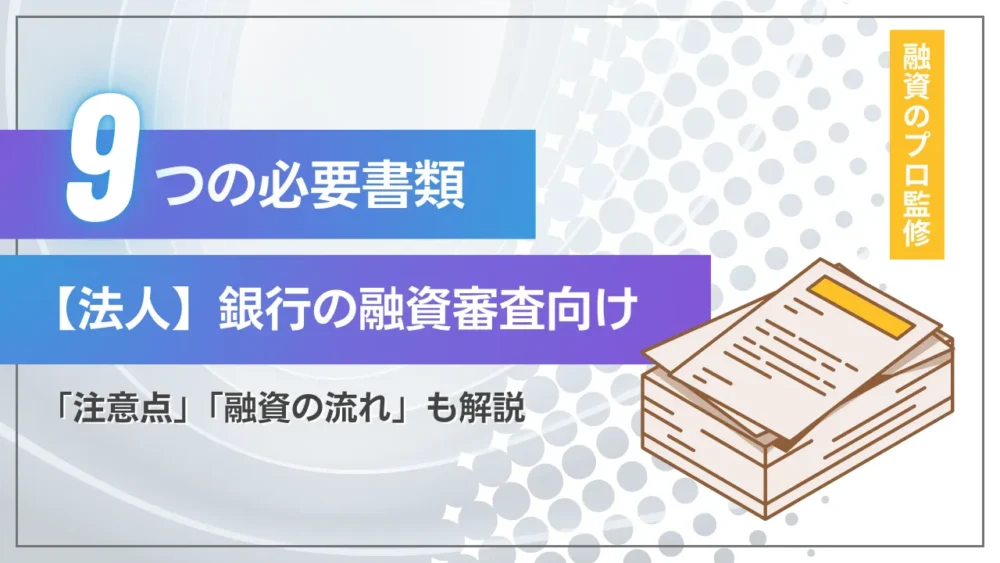
ポイント1. 明確な「資金使途」と「融資額」
「融資(借入)の一本化」の審査ポイント1つ目は、明確な「資金使途」と「融資額」です。
一本化をするのであれば、「どの金融機関から」「どのくらい」「どんな融資条件で」借りているのかを把握して、金融機関への融資の一本化を打診するべきです。その際には、融資の一本化で「どんな効果が期待できるのか」、資金計画や根拠になる資料も揃えておくと良いでしょう。
例えば、以下のような資料や書類が有効です。
- 事業計画書
- 資金繰り表
- 見積書
- 金融機関からの借入状況一覧表
- 返済予定表 など
また、融資の一本化で必要な金額についても明確な根拠を用意しておきましょう。
仮に、融資(借入)の一本化を説明するのに十分な「資金使途」や「融資金額」を経営者が把握していない場合は、「感覚で経営・資金繰りをしている経営者」という印象がつく危険性がありますので、しっかりと考えてから金融機関には打診しましょう。
ポイント2. 緻密な「事業計画書」と「資金繰り表」
融資(借入)一本化の融資審査にとおるには、「事業計画書」や「資金繰り表」作成すると良いでしょう。「事業計画書」で、今後どのように事業を展開していくかを示します。「資金繰り表」では、今後の入金と出金のバランスを示します。
金融機関は、融資の一本化を打診してきた企業の、将来の精緻な資金繰りと、その根拠となるもの(事業計画)を評価して、融資の可否を決定します。とくに考慮されるのは以下のような点です。
◆ 事業計画書と資金繰り表で重視されること
- 今後事業がどのように成長するのか
- 融資の一本化が、どんな効果を生むのか
- 一本化しても、返済は滞らないか
- そもそも、資金繰りの目途はあるのか
精緻な「事業計画書」と「資金繰り表」は、金融機関の懸念を払拭するのに役立ちます。その上で、経営者が自ら「事業計画書」や「資金繰り表」について正しい説明ができれば、金融機関の安心度合いはさらに増すため、絶対におこないましょう。
なお、「銀行融資向けの事業計画書の作り方」や「銀行向けの資金繰り表の作り方」について詳しく知りたい方は、以下の記事が参考になるので必ずチェックしておきましょう。


ポイント3. 担保・保証人をつける(必要に応じて)
融資の一本化をしたい理由が「会社の資金繰りが厳しい」といったの場合には、金融機関からよい返事は期待できません。そんな時は、「担保・保証人」を付けることで融資審査に通りやすくするテクニックを使いましょう。
特に以下の状態の場合は、融資審査ではマイナスです。
◆ 融資審査でマイナスな会社の状態
- 赤字経営である(2期以上続いていると、更に厳しい)
- 売り上げが低い
- 利益が薄い
- 債務超過
- 手元の現預金が少ない(月商の2ヶ月以下)
現在では無担保・無保証でも融資が受けられる金融機関や商品も多くなりましたが、もし価値のある不動産を持っていたり、経営者保証(保証人)になっても大丈夫な場合には、それを交渉材料に一本化ができる可能性があります。
ただし、原則、担保や保証人に頼りすぎないことが重要です。
日本政策金融公庫、商工中金、地銀、信用金庫・信用組合の融資は、知識・経験なく「何となく」で進めると必ず失敗します。融資には「金融機関の理解」と「ノウハウと実務経験」が必要です。
融資代行プロは、金融機関出身のコンサルタントが「成果報酬型1%~」で融資コンサル/代行するサービスです。これまで5,600社以上の融資相談を受け「200万円〜9.5億円の融資成功」の実績を挙げてきました。
そんな私達に無料の融資相談をしませんか?詳細は下記ページをご覧ください。
成果報酬型の融資コンサルはコチラ>
\「融資の一本化」成功率が上がる/
※【毎日 限定5名まで】
融資・借入を一本化する「4つのメリット」
返済額を減らし、さらなる借入を可能にするためにも、資金調達で借入を一本化するメリットを詳しく知っておくべきです。融資・借入の一本化によるメリットは以下4つです。
- メリット1. 毎月の返済額が減る(資金繰りが楽になる)
- メリット2. 返済日の管理がしやすくなる
- メリット3. さらなる借入がしやすくなる
- メリット4. 返済計画が立てやすくなる
それぞれ、詳しく解説していきます。
メリット1. 毎月の返済額が減る(資金繰りが楽になる)
資金調達で借入を一本化する最初のメリットは、毎月の返済額を減らせる点です。
金融機関からの融資は、借入金額が大きくなればなるほど金利が低く設定されています。複数の金融機関や消費者金融から少額の融資を受けるよりも、借入を一本化して1社から多額の融資を受けたほうが月々の返済額は減るでしょう。
たとえばある企業がA信金社から2,000万円、B信金社から2,000万円、C銀行から3,000万円、合計7,000万円の借入をしているとしましょう。その上で、月々の返済額はA信金社が20万円、B社が25万円、C社が40万円の合計85万円であるとします。
▼3つの金融機関から複数借入している場合
| A信金 | B信金 | C銀行 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|
| 借入額(万円) | 2,000 | 2,000 | 3,000 | 7,000 |
| 返済額(万円) | 20 | 25 | 40 | 85 |
しかしこれをD銀行で一本化し7,000万円の借入にすれば、下の表にあるように最初の3社よりも低い金利が適用され、借入総額は変わらなくても毎月の返済額を85万円以下にできるかもしれません。
▼1つの金融機関に一本化した場合
| D銀行 | |
|---|---|
| 借入額(万円) | 7,000 |
| 返済額(万円) | 70 |
これはあくまで例ですが、返済期間を延ばすことができれば、毎月の返済額をさらに減らし資金繰りをより容易にできるでしょう。業績や返済計画によっては、毎月の返済額は現在と同じ85万円のままで、さらにD銀行から借入を行うこともできるかもしれません。
融資・借入を一本化すれば、返済の負担を減らしつつ、さらなる資金調達への道が開けます。
メリット2. 返済日の管理がしやすくなる
借入先を一本化することで、返済の管理がしやすくなります。
借入先が複数あると返済日を忘れてしまったり、口座に十分な残高を用意できなかったりするかもしれません。資金繰りをしつつ、複数ある返済日に十分な残高を確保しておくのは難しいと感じる経営者の方も少なくないでしょう。
そして万が一、残高の確認を忘れて返済が滞ると、信用情報に支払いの遅延が記録されて、将来予定している借入が難しくなる恐れがあります。円滑な資金調達を行ううえで、複数の借入先があるのはリスクとなり得るのです。
もし資金調達による借入を一本化できれば、毎月1度の返済日に備えるだけで済みます。その日までに十分な残高を用意しておけばよいので、資金繰りが容易になるでしょう。
メリット3. さらなる借入がしやすくなる
融資・借入を一本化することで、さらなる借入がしやすくなるというメリットもあります。
金融機関は融資を実行するかどうかを決定する際、申請者の借入先の数をチェックします。もしすでに複数の企業から借入をしている場合、本当に返済可能かを懸念されるため審査に通りにくくなります。
金融機関としては、自社への返済が後回しにされるのを恐れて融資に慎重にならざるを得ないのです。
一方多額の借入であっても、借入先が1社であれば印象はまったく変わります。1社からの借入であれば返済計画も立てやすく、金融機関も安心して融資を実行することができます。
融資・借入を整理したうえで、さらなる資金調達が可能になる場合もあるのです。
メリット4. 返済計画が立てやすくなる
融資・借入を一本化しておけば、返済計画が立てやすいです。
複数の金融機関や貸金業者から借入を行っている場合、今の借入の総額がいくらなのか、今の返済額でいつ返済が終わるのかなどを把握するのが難しくなります。結果として返済計画を立てられず、返済に窮してしまう企業も少なくありません。
融資・借入を一本化すると以下の計画が立てやすくなります。
◆ 一本化で計画が立てやすくなる項目
- 現在の借入額
- 毎月の返済額
- 返済が終わる時期
- 返済総額
売り上げが伸びてきたら毎月の返済額を増やして返済を早く終わらせたり、可能であれば繰り上げ返済を利用したりして返済総額を減らすこともできるでしょう。
日本政策金融公庫、商工中金、地銀、信用金庫・信用組合の融資は、知識・経験なく「何となく」で進めると必ず失敗します。融資には「金融機関の理解」と「ノウハウと実務経験」が必要です。
融資代行プロは、金融機関出身のコンサルタントが「成果報酬型1%~」で融資コンサル/代行するサービスです。これまで5,600社以上の融資相談を受け「200万円〜9.5億円の融資成功」の実績を挙げてきました。
そんな私達に無料の融資相談をしませんか?詳細は下記ページをご覧ください。
成果報酬型の融資コンサルはコチラ>
\「融資の一本化」成功率が上がる/
※【毎日 限定5名まで】
融資・借入を一本化する「4つのデメリット」
融資・借入を一本化することには多くのメリットがあります。しかし借入の一本化にはメリットだけでなく、デメリットも存在します。融資・借入の一本化によるデメリットは以下の4つです。
- メリット1. 借入総額は変わらない
- メリット2. 返済総額が増える恐れがある
- メリット3. 審査に通るとは限らない
- メリット4. 返済期間が長くなることがある
デメリット1. 借入総額は変わらない
借入を一本化したところで、借入総額が減るわけではありません。
たとえばA社から2,000万円、B社から2,000万円、C社から3,000万円と3社からの借入を一本化しても、7,000万円の借入があるという事実は変わらないのです。
毎月の返済額を調節したり、返済期間を延ばしたりすることは可能ですが、一本化によって借入額が減ることはないので注意しましょう。
デメリット2. 返済総額が増える恐れがある
借入の一本化によって、返済総額が増える危険性もあります。
借入を一本化して、毎月の返済額を変えなければ返済総額は増えません。しかし平成22年の貸金業改正により、 ”「一ヶ月の負担額」について、「借換後」の負担額が、「借換前」の負担 額を上回らないこと ”と定められているため、ほとんどの場合借入を一本化したあとは毎月の返済額が減ります。
[引用元]金融庁:改正貸金業法に関する内閣府令の改正の概要[PDF]
借入額が変わらず、毎月の返済額が減るため、返済期間が延びていく可能性が高くなります。返済期間が延びると支払う利息が増え、その結果、返済総額が増えることになるのです。
デメリット3. 審査に通るとは限らない
資金調達で借入を一本化したいと思っても、金融機関の審査に通らないことも考えられます。もし審査に通らなければ、一本化はできず別の方法での資金調達が必要となるでしょう。
借入の一本化では、1社から受ける融資の金額が大きくなります。金融機関側としても、返済能力に疑問がある場合には審査を厳しくしたり、より低い金額での融資を決定したりせざるを得ません。
資金調達で借入を一本化しようと思ってもうまくいかず、再度資金調達のための計画を練り直さなければならないということもあるでしょう。
デメリット4. 返済期間が長くなることがある
借入を一本化する際の4つ目のデメリットは、返済期間が長くなることです。借入を一本化すると、毎月の返済額を見直して無理のない範囲で返済ができます。
それ自体は大きなメリットですが、毎月の返済額を少なくしすぎると返済期間がかなり延びてしまいます。最初に借入を行ったときの想定よりも返済期間が大幅に延びると、その後の会社の業績に影響を与える恐れもあるでしょう。
借入の一本化を検討する場合には、毎月の返済額と返済期間のバランスが大切です。
「融資(借入)の一本化」は、融資コンサルタントに相談するのがおすすめ
現在、複数の金融機関から融資を受けており、一本化して資金繰りを楽にしたい経営者の方は、融資に強いコンサルタントにアドバイスを求めるのがよいでしょう。融資に強いコンサルタントに相談すべき理由は、以下3つです。
- 理由1. 豊富な知識・経験で、成功率が上がる
- 理由2. 融資の書類作成支援・面談対策
- 理由3. 短期間での融資実行が可能
それぞれ、詳しく解説していきます。
理由1. 豊富な知識・経験で、成功率が上がる
まず資金調達のプロは、長年蓄積された経験による的確なアドバイスを行えます。
借入を一本化できるのか、別の資金調達方法のほうがより多くの資金を集められるのかといった情報も提供してくれることでしょう。長年資金調達に携わってきたスペシャリストが在籍している場合もあるので、心強い味方になってくれるはずです。
理由2. 融資の書類作成支援・面談対策
一般的に経営者の方は、本業をこなしながら資金調達を行います。本業が忙しすぎて資金調達にまで手が回らないということもあるでしょう。
そんなときに融資のプロに頼れば、以下業務などを支援してくれます。
◆ 融資のプロに支援してもらえること
- 事業計画書や資金繰り計画書などの書類作成
- 金融機関との面接の日程調整
- 実際の面接への同伴
- 面接の代行
その結果、資金調達に時間や労力を奪われることなく、本業に集中することができるのです。
理由3. 短期間での融資実行が可能
資金繰りが厳しい経営者の方であれば、できるだけ早く借入を一本化したいと考えていることでしょう。融資のプロに相談すれば、短期間で融資を受けるための支援が受けられます。
正確な書類作成、融資担当者からの質問に対するふさわしい回答、金融機関を納得させられる経営の改善策などにより、ご自分だけで借入を一本化するよりもかなり短い時間で資金調達が行えるでしょう。
日本政策金融公庫、商工中金、地銀、信用金庫・信用組合の融資は、知識・経験なく「何となく」で進めると必ず失敗します。融資には「金融機関の理解」と「ノウハウと実務経験」が必要です。
融資代行プロは、金融機関出身のコンサルタントが「成果報酬型1%~」で融資コンサル/代行するサービスです。これまで5,600社以上の融資相談を受け「200万円〜9.5億円の融資成功」の実績を挙げてきました。
そんな私達に無料の融資相談をしませんか?詳細は下記ページをご覧ください。
成果報酬型の融資コンサルはコチラ>
\「融資の一本化」成功率が上がる/
※【毎日 限定5名まで】
融資(借入)を一本化して、資金繰りを大幅に改善しよう
資金調達で今の借入を一本化することができれば、返済日の管理が楽になるだけでなく、会社全体の資金繰りが容易になることでしょう。融資の一本化の融資審査では、以下3つのポイントをおさえて臨みましょう。
3つの審査ポイント
- ポイント1. 明確な「資金使途」と「融資額」
- ポイント2. 緻密な「事業計画書」と「資金繰り表」
- ポイント3. 担保・保証人をつける(必要に応じて)
本記事はここまでになりますが、融資の現場で培ったリアルで濃い内容なので、「ブックマーク」して、あとから何度も読み返すことをオススメします。
なお、筆者の経営する「融資代行プロ」では、難しい銀行借り入れの一本化を成果報酬型のコンサルティングでご支援しています。書類作成の作成支援や融資面談の助言など、借入の一本化を成功させるためにきめ細やかなサポートを行います。「融資代行プロ」で短時間・低コスト、かつ有利な資金調達や借入の一本化を成功させましょう。
日本政策金融公庫、商工中金、地銀、信用金庫・信用組合の融資は、知識・経験なく「何となく」で進めると必ず失敗します。融資には「金融機関の理解」と「ノウハウと実務経験」が必要です。
融資代行プロは、金融機関出身のコンサルタントが「成果報酬型1%~」で融資コンサル/代行するサービスです。これまで5,600社以上の融資相談を受け「200万円〜9.5億円の融資成功」の実績を挙げてきました。
そんな私達に無料の融資相談をしませんか?詳細は下記ページをご覧ください。
成果報酬型の融資コンサルはコチラ>
\「融資の一本化」成功率が上がる/
※【毎日 限定5名まで】】
_20250924.png)


